この記事でわかること
• 病気・ケガで退職するときの実務フロー(休職/退職の判断、離職理由、社会保険の切替)
• 傷病手当金の受給条件・金額・退職後の継続受給(申請のコツ・不支給を避ける注意点)
• 医療費控除・高額療養費・セルフメディケーション税制の使い分けと実務
• 復職(職場復帰)に向けた準備(産業医・主治医・リワーク、段階的復職の設計)
• 20代/30代/40代/50代以上の年齢別に変わる戦略

病気・ケガでの退職手続き:休職か退職か、まずはここを整理
最初の判断:休職で回復を待つか、退職するか
• 就業規則の〈私傷病休職〉条項と最長休職期間を確認
• 主治医の診断書:就労可否・就業配慮の要否・想定期間を明記してもらう
• 会社側の配慮(短時間勤務、配置転換、在宅等)が可能か
• 退職を選ぶ場合の離職理由:病気等やむを得ない事情は**「特定理由離職者」**該当の可能性(給付の扱いに影響。ハローワーク判断。診断書等のエビデンスが重要)(グスクード社会保険労務士事務所 | 沖縄・那覇の労務管理・助成金・外国人雇用 -)
退職の申出タイミング(法律の目安)
• 期間の定めがない雇用は、民法627条1項により申出から2週間で退職が可能(就業規則の「◯カ月前申出」は原則、労働者の退職の自由を不当に制限する特約は無効とされる裁判例も)。ただし実務上は引継ぎ配慮や就業規則の内部手続に沿うのが無難。
退職~直後の社会保険&年金:48〜20日ルールに注意
• 健康保険の選択
◦ 勤務先健保の任意継続:退職日の翌日から20日以内に申請、かつ被保険者期間が通算2カ月以上。ただし任意継続中に発生した新たな傷病では傷病手当金は出ない。保険料は会社負担がなくなるため上がりやすい。
◦ 国民健康保険:前年所得で保険料が決まりやすく、大幅減収の1年目は割安になるケースも。世帯単位、扶養の扱いに差。比較して選ぶ。
• 年金:次就職まで間が空くなら国民年金第1号へ切替。配偶者の扶養に入るなら第3号の手続き。
雇用保険(失業手当)×病気のときの扱い
• 病気で求職できない期間は基本手当は受けられないが、受給期間の延長が可能(最長3年延長、本来の1年に加算)。30日以上働けない状態が目安。診断書等が必要。
• 後述の傷病手当金と同時受給は不可(制度趣旨が異なるため)。開始時期の調整や延長届での順番設計が肝。
傷病手当金の申請方法:条件・金額・退職後の継続受給
受給条件(要約)
1. 業務外の病気・ケガで療養中
2. 労務不能(医師の意見書が重要)
3. 待期3日を含む4日目以降(3日連続の休業が必要)
4. 休業期間中に給与が出ていない(出ていても額が少なければ差額支給)
5. 支給期間は通算1年6カ月(2025年時点)
※任意継続中に新たに発生した傷病は対象外。退職後の継続給付の可否は次項へ。
いくらもらえる?
• 1日あたり 標準報酬日額 × 2/3 を基本に算定(直近12カ月の標準報酬月額平均などのルールあり)。詳細は加入する保険者の算定例を参照。
退職後もらい続けられる?(資格喪失後の継続給付)
• 退職時点で待期完成+労務不能が継続しており、かつ在職中に受給していた・受給可能な状態で、被保険者期間1年以上などの要件を満たせば通算1年6カ月の範囲で退職後も継続受給が可能。退職後に一度でも労務可能と判断されると、その後の受給は原則不可。
1. 主治医に「労務不能」の証明(就労不可期間を明確に/通院間隔が空きすぎない)
2. 事業主証明(賃金支給状況、休業日数)—退職後は前職へ依頼
3. 健康保険の保険者へ申請
4. 不備防止:休業日・給与支給の突合、待期3日の連続性、離職票の内容と整合
5. 受給中の注意:副業・短時間労働・求職活動は労務可能性と見なされうる
よくある不支給要因
・診断書と勤務実態の齟齬/アルバイト・転職活動の実施
・「待期3日」未完成/給与の発生(有休含む)との重複
・退職日当日の出勤で「継続給付」要件を欠く
医療費控除と税金対策:高額療養費との合わせ技で手取り最大化
まずは高額療養費制度で現金流出を抑える
• 1カ月(暦月)の自己負担が所得区分ごとの上限額を超えた分が払い戻し。
• 事前に「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証)を提示すれば窓口支払いを上限額までに抑制可能。
• 対象は保険適用分のみ。入院食事代・差額ベッド代は対象外。世帯合算・多数該当などの軽減も。
• 計算式:
(実際に支払った医療費 − 保険金等で補填された額) − 10万円
ただし総所得金額等が200万円未満は10万円ではなく5%。上限は200万円。
• 代表的な対象:診療費、処方薬、通院交通費(原則公共交通機関)、治療用器具、助産師の費用 等。タクシーは原則対象外(緊急や公共交通不可の場合等を除く)。
• 明細書の添付が必要。領収書は自宅で5年間保管。e-Tax対応。
セルフメディケーション税制との選択
• 年間1.2万円超の対象OTC薬購入で使える特例。通常の医療費控除と同時適用不可(選択適用、後からの切替も不可)。
実務Tips
• 高額療養費で後日支給された額は、その給付目的となった医療費から差し引き(他の医療費からは控除しない)。
• 交通費は区間・金額メモ(IC履歴・明細に残す)。付添い交通費は患者が一人で通院できない場合のみ対象。
復職に向けた準備:主治医・産業医・職場で三位一体の設計を
復職戦略の基本セット
1. 医療面:症状安定、服薬調整、主治医の就労可否意見
2. 職場面:産業医面談、人事・上司との復職計画(就業制限・配慮)合意
3. リハビリ:リワークプログラム(医療機関の精神科デイケア等)、段階的就労(短時間→時短解除)
• 厚労省の「職場復帰支援の手引き」は、休業判定→準備→試し出勤→本復帰までのプロセス設計が実務的。
• 治療と仕事の両立支援サイトは、職場への情報開示の範囲・伝え方の考え方が参考。
段階的復職プラン(例)
• 週3日×1日4h → 週4日×6h → 週5日×6h → フルタイム
• 評価ポイント:通勤負荷、集中持続、対人ストレス、業務量、残業の有無
年齢別:退職判断と資金戦略のちがい
20代
• キャリアの再設計余地が大きい。在職中の休職活用+復職 or 短期療養後の転職も現実的。
• 傷病手当金と受給期間延長で現金流を確保し、スキルのリスキリング着手を早めに。
30代
• 住宅・家族費用で固定支出が重い層。高額療養費+医療費控除の併用で手取り改善。
• 転職前に症状安定→試し出勤→在宅可否の条件交渉。任意継続 vs 国保は保険料と扶養でシミュレーション。
40代
• 職責が高く配置転換や裁量縮小の合意形成が鍵。
• 障害年金(長期・重度の場合)の要件確認を早めに。初診日要件・納付要件が重要。
50代・プレ定年層
• 老齢給付までのブリッジを意識:傷病手当金→障害年金や雇用保険の延長の時系列設計が重要。
• 家族の介護・医療費も増える傾向。多数該当・世帯合算の適用を押さえる。
すぐ使える実務チェックリスト
退職前〜直後
• □ 就業規則(休職・退職条項)確認
• □ 診断書(就労不可期間・配慮事項)取得
• □ 退職日と最終出勤の決定(退職日出勤は避ける:継続給付に影響)
• □ 健康保険の選択(任意継続:20日以内/国保)手続き
• □ 年金(第1号 or 第3号)切替(年金するポータル)
• □ 離職票の離職理由の確認(病気事由の証憑保管)
• □ 雇用保険の受給期間延長(30日以上就労不能時)申請可
傷病手当金
• □ 待期3日の連続休業を確保(有休の扱いに注意)
• □ 事業主証明・医師意見書・賃金台帳等を整える
• □ 退職後の継続給付要件(1年以上加入、退職時点で受給中/受給可能、労務不能継続)
医療費控除・高額療養費
• □ 限度額適用認定証を事前取得(窓口支払い圧縮)
• □ 医療費控除の明細書作成、領収書は5年保管
• □ 通院交通費は区間・金額を記録(公共交通機関が原則)
• □ セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択制(同時不可)
復職準備
• □ 主治医の就労可否意見書/産業医面談
• □ 段階的復職案(時短→段階拡大)を職場と設計
• □ リワークプログラムの利用可否を検討(医療デイケア等)
ケースでわかる「順番の正解」
ケースA:退職して療養→その後に求職
1. 在職中に傷病手当金を開始(待期3日を満たす)→
2. 退職(退職日出勤なし)→継続給付で生活資金を確保→
3. 症状安定後、雇用保険の受給期間延長を解除して求職開始
ポイント:傷病手当金と失業手当の同時受給不可。順番設計が最重要。
ケースB:医療費が嵩む長期治療
• 限度額適用認定証で当月の窓口負担を上限までに抑える→
• 翌年の医療費控除で税負担を軽減(高額療養費の支給額は補填分として差引)。

よくある質問(簡潔版)
Q. 傷病手当金はいつまで?
A. 通算1年6カ月。原則延長なし(同一傷病の範囲で算定)。
Q. 退職後に初めて病気になったら?
A. 任意継続には傷病手当金制度なし。国保は原則制度なし(自治体や組合による特例は別)。
Q. 医療費控除の交通費は?
A. 公共交通は対象。タクシーは緊急や公共交通不可の場合のみ。
Q. 失業手当はいつ申請?
A. 求職できる状態になってから。病気で不可なら受給期間延長を先に。
参考・一次情報(主要)
• 傷病手当金の条件・額・待期・継続給付(協会けんぽ)
• 退職後継続給付の要件(厚労省/協会けんぽ解説)(こころの耳)
• 高額療養費制度・限度額認定(厚労省、健保)(厚生労働省)
• 医療費控除(国税庁 No.1120、明細書・保存、対象範囲・交通費、セルフメディケーション税制)(国税庁)
• 退職の法的根拠(民法627条:e-Gov/厚労省解説)(e-Gov 法令検索)
• 雇用保険の受給期間延長(厚労省・ハローワーク)(厚生労働省)
• 復職プロセス(職場復帰支援の手引き、両立支援)(厚生労働省)
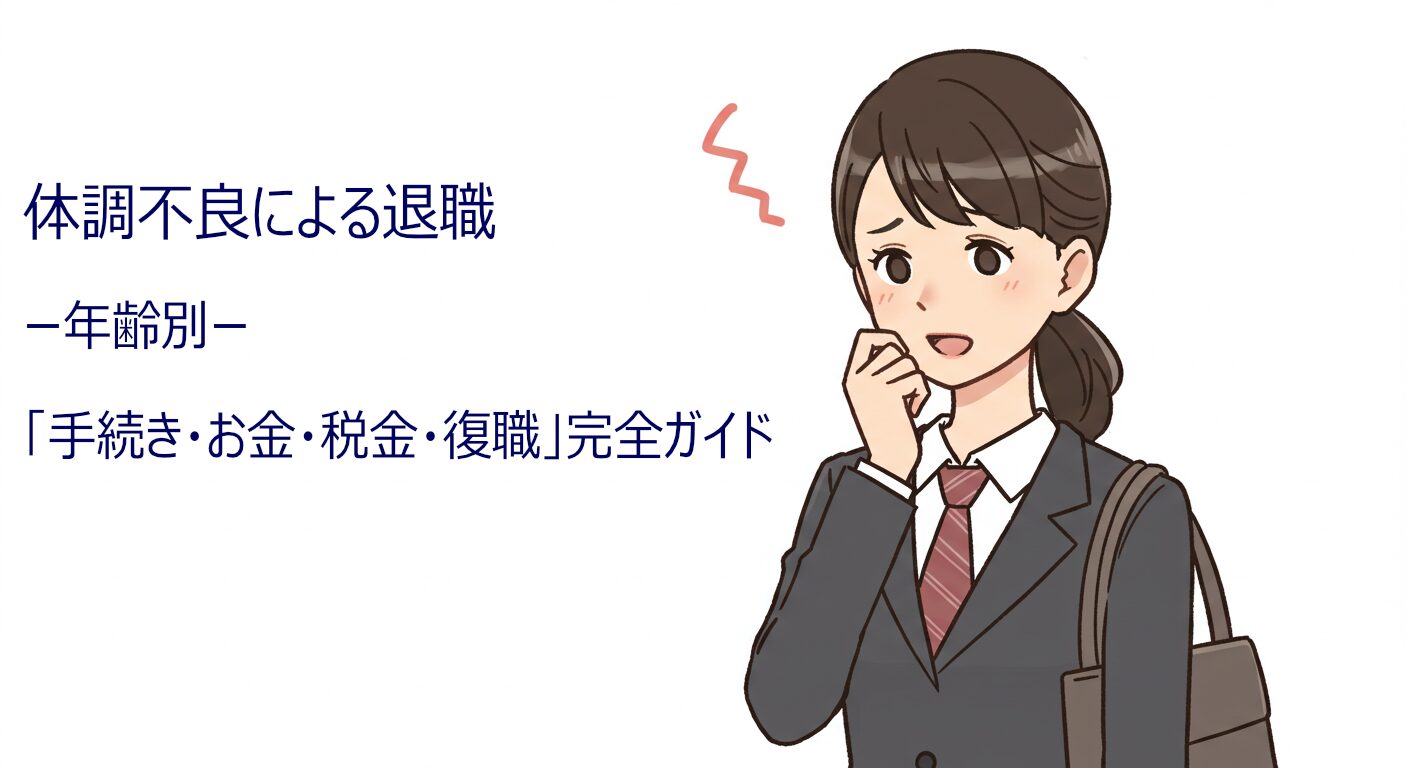


コメント